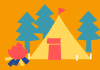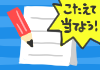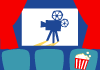「子供にどんな本を与えたらよいか」という質問を「いこーよ」ユーザーの皆さんからいただくことが多い。二人の子供の育児中の自分の経験からも、子育てに児童書や絵本は欠かせない存在だ。
一方、出版業界では「インターネットに費やす時間が増えて本を読む時間が減った」、「電子書籍が普及した」など様々な原因で本が売れない中、意外にも児童書の売上は伸びている(下表参照)。
今回は、児童書の中でも「いこーよ」ユーザーの関心の高い絵本の現状について現場を取材した。

出版不況に負けない絵本の魅力

「大好きな雑誌や本が手元に置いてあると、ホッとします」と話してくれたのは、今年新卒で日本出版販売株式会社に入社した浦西里奈さん。書籍、雑誌、コミックまで、本という本が大好きで、全国に数多くある出版社と書店の間をつなぐ、出版流通業界を希望した。出版不況の現実は入社してから日々実感することになる。

「和歌山エリアを中心に書店を担当しているのですが、どのお店の方もお客さんが減っているのがとても寂しいと口を揃えておっしゃいます。実際に書店の売り上げも右肩下がりですし、書店の数も年々減っています」
そう言って見せてくれたデータには年々書店数や書店売り上げが減少していることが記されていたが、浦西さんの表情は穏やかで明るい。
「日々フェアやイベントなど様々な方法を取り入れて、一つでも多くの書店が元気になるような仕組みを作っていきたい。特に、不況といわれる中でも売り上げを伸ばしている絵本のジャンルでは、読み聞かせのイベントをしたり、絵本それぞれの魅力が伝わるように表紙をしっかり見せるような売り場作りをしたり工夫を積み重ねています」
また、これからのクリスマスシーズンに向けて、絵本の需要はさらに伸びるという。
「絵本をギフトにと考えてくださるお客様は多くおります。お孫さん向けに絵本をシリーズでまとめて購入してくださる方もいらっしゃいますし、単価が通常の絵本よりも高い仕掛け絵本をプレゼントにと購入される方も増えます」
クリスマスに絵本をプレゼントしたくても、何をプレゼントしていいかわからない時はどうしたらいいのだろうか。
「書店の店員さんはそのお店でどの絵本がよく売れているかよく知っているので、売れ筋から絵本を選びたいという際には、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。また、関西エリアではこれからクリスマスにかけて『2017関西書店祭』を開催します。育児中のパパ・ママによる絵本ランキングなども売り場に掲載するので、ぜひ参考にしていただき、絵本を手に取ってみてください。絵本を通じて、子供の頃の思い出を振り返ってみたり、絵本をきっかけに家族の会話につながったりすると嬉しいですね」
出版業界を明るく見つめる浦西さんの優しい笑顔がとても印象に残った。

2017関西書店祭は、11月3日(金)から12月17日(日)までの45日間、関西エリアを中心に150店舗ほどの書店で開催される。
2017関西書店祭についてはこちら社員の出産祝いに社長自ら選んだ絵本を贈る出版社

「美しいものに囲まれていたいじゃない」と話す干場さん。大人になって着る服、家のインテリアや片付いた空間、それらは今までに形成された美意識が影響していると話す。幼少期の環境が重要と考え、美しい絵本を見せる重要性を訴えかける。
「あかちゃんは原色が好きっていうような説も聞きますが、そうした定説に疑問を抱いたのが出発点。あかちゃんに対しても、もっと色々な色を使って、情緒を育成し視覚を育てることが大切じゃないかしら」
また、スマホのブルーライトを受けるよりも、太陽光で、自然光のもとで様々な色彩を感じてもらい、紙の感触も感じてもらいたいという思いから、絵本の電子書籍化は現在していないという。

同社のあかちゃん学絵本シリーズは今までの絵本にはない発想で企画されている。「あかちゃんが本当に好きな絵や色は何か?」という視点だ。従来の絵本は、大人の視点で「子供が喜ぶだろう」と考えて描かれている。あかちゃんや子供がその絵本を「いい」と判断するのは、完成した本を手にした段階になる。
それに対して、このシリーズはどんな絵や色をあかちゃんは好むのかということをスタートの段階から考えて作られている。「あかちゃん学」を研究する「東京大学あかちゃんラボ」の協力のもと作られた、世界でも珍しい「あかちゃんと作ったあかちゃんのための絵本」だ。
「大人が思っているあかちゃんの好きそうなものと、本当にあかちゃんが好きなものって違うのかもしれないという仮説を立てて実際に実験してみたところ、お母さんの好きなものとあかちゃんが長く見つめるものに違いがありました。だったら、あかちゃんが選ぶものを絵本にしようという発想です。そんなふうにして、できあがったのが『うるしー』『モイモイとキーリー』『もいもい』の3冊です」
常識に疑問を持ち、こうした科学的な検証を行う背景にあるのは、干場さんの本と子供への思いだ。子育てにセンシティブになってしまう親に、自信をもって我が子に本を選んであげるための指標を提示したい。

「先日うちの社員の出産祝いに絵本を贈ったのですが、結果的に選んだ絵本の多くは私が子育て中に子供に与えたことのあるものがほとんどでした。絵本は親が自分の過去の経験で選ぶので、新しい本を選んでもらうのが難しい。だから定番の本が売れ続ける。ロングセラーも大切ですが、新しい本が生まれることも重要。幼少期の子供達の美的感性を磨くために、絵本は大切な存在ですから。出版社としては、このシリーズのように絵本に新しい価値を加えチャレンジをする必要があります」

絵本に限らず子供に与えるもの選びに悩む人は多い。このシリーズに応用されたようにあかちゃんの意識についての研究は様々な面で進んでいる。選択に迷う際には科学的知見を判断基準の一つの要素として取り入れることも大切だろう。

今回紹介したあかちゃん学絵本(『うるしー』『モイモイとキーリー』『もいもい』)を各5名様、合計15名様にプレゼント。ご希望の方は下記のフォームからご応募ください。(応募締切:2017年11月15日(水) 13:00)
読者プレゼント応募はこちらから自由な発想で常に挑戦を続ける絵本作家

「周りは絵本作家といっているけど、絵本は僕たちにとって仕事の一部分。絵本は自分達が楽しいから作ってる」
アートユニットtupera tupera(ツペラ ツペラ)の亀山達矢さんの絵本作りに対する視点だ。
先々の目標があるのがあまり好きではない。いつも何がおこるかわからないワクワクする感覚をもっていたいという思いがあるからだ。
絵本作りは周りの声に押され、1冊作ってみようかなという気持ちでスタートした。当時、雑貨ブームで雑貨屋には海外のおしゃれな絵本が並んでいるのを見てカッコイイと感じていたことから、インテリアになるような絵本だったら作ってみたいと感じた。
自分達で印刷所を探し、1,000部刷った。100万円以上かかった。絵本の売り込みはしなかった。時間があったら作品作りに注ぎたいからだ。自分たちの小物を置いてくれているお店に置かせてもらったら、絵本は半年で売り切れた。

その最初の絵本が『木がずらり』だ。その後、『やさいさん』や『くだものさん』、『しろくまのパンツ』、『パンダ銭湯』など数多くの作品を生み出した。tupera tuperaはアイデアに合わせてその都度、画材や技法を変えている。同じようなことを続けていくのではなく、1冊ずつ面白いことに挑戦していきたいという。
「でも、今、絵本の世界は面白い時代になってきていると思いますよ。30代から40代の絵本作家さんに刺激的で面白い方が多いな、と」
本屋さんに行くと、他の作家の絵本を手に取ってみる。個人的に抵抗のある絵のものもとりあえず開く。読んでいくうちにいつの間にかその絵が好きになっていることがあるという。新しい作品のもつ新しいパワーがそこにあるのだそうだ。

絵本にかける思いについて聞いてみた。
「僕らは子供にだけ向けた絵本作りはしていません。こういうと、勘違いされることもありますが、誰しもが子供の心をもっていると思っているので、0歳から、それこそ100歳までに向けて作っています」
絵本は世代を超えてお互い共感し合えるプロダクトであるというのが思いとしてあるのだ。これからもたくさんの面白さを作り出していくであろう現代の絵本作家から目が離せない。
読み手と作家をつなぐ美術館の取組み

前出のtupera tupera(ツペラ ツペラ)の展覧会が開催されている横須賀美術館。
「横須賀美術館は2007年からtupera tuperaさんとワークショップの開催などでお付き合いがあり、今回の企画はtupera tuperaさんの結成15周年と横須賀美術館10周年というそれぞれの節目に実現しました」
今回の展覧会は、原画でしか見ることのできない切り絵のテクスチャー(表面の質感)を間近に見られる貴重な機会。大人ほど原画には興味のない子供であっても、やはり一度絵本で目にしたことのある作品には自ら歩み寄り、注意深く見ているそうだ。
- 作品にさわらない
- 走らない
- 人に迷惑をかけない
美術館は子供連れにとってハードルが高いお出かけ先だと思っていたが、周りを見回すと子供連れが多い。
「横須賀美術館では、なるべく年に1回は家族で楽しめるような企画展を開催しています。幼い頃から美術館に親しむことが、大人になった時に美術館に気軽に来られる流れにつながるのではないかと思っています」
企画展のテーマにもよるが、今回のような家族でも楽しめるような内容の場合は、気軽に子供を連れてきてほしいと言う。ちょうど、そばを走り回っている子供達をみつけた中村さんがその子供達に「美術館ではお約束があります。『作品にさわらない、走らない、人に迷惑をかけない』この3つのお約束を守ってくれるかな?」と笑顔で優しくマナーを伝える様子をみて、美術館は子供達にとって公共のマナーを実践で学ぶ場でもあるのだと感じた。
「美術館で見たり体験したりしたことが家族の会話のきっかけになったら嬉しいですね」
中村さんお言葉どおり、美術館は子供に素敵な経験を与えてくれる場だ。うちの子供たちとの「お出かけリスト」に美術館も加えることにしよう。
今回ご紹介した横須賀美術館の「ぼくとわたしとみんなの tupera tupera 絵本の世界展」は11月5日(日)まで開催されている。

tupera tupera の絵本作りの工程を見ることができたり、

入口で『しろくまのパンツ』のしろくまと写真を撮ることができたり、

『パンダ銭湯』を再現した湯船につかることもできる。
なお、11月3日(祝・金)は入場料無料になるが、パンダ銭湯は撮影不可になるとのこと。記念写真を撮りたい方は要注意だ。
■ぼくとわたしとみんなの tupera tupera 絵本の世界展
開催日時:2017年9月9日(土)〜11月5日(日)
場所:横須賀美術館
観覧料:一般900円、高校生・大学生・65歳以上700円、中学生以下無料
※市内在住または在学の高校生は無料
※11月3日(祝・金)は無料