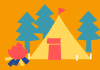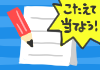サラダやお刺身、魚卵といった生もの。カラシやワサビといった強烈な香辛料。卵やそばなどアレルギーが出やすいものなど、ちょっと心配な食材たち。これって、幼い子どもが食べても大丈夫なんでしょうか? 栄養士さんに解禁のタイミングを聞きました!
食べ物の解禁、「年齢」は目安になるのか!?

だんだんと色んなものを食べられるようになると、「あれ、これ食べさせちゃって大丈夫だっけ?」と心配になる食材も増えてきますね。
「3歳頃からはけっこう何でも食べさせてます!」との声も聞きますが、実際のところ、何歳くらいからなら、食べさせて良いのでしょう? 幼児の食に詳しい栄養士の梅原充子先生に聞いてみましょう!
「残念ながら、食材に関しては数字で示せるような“解禁年齢”はありません。乳幼児のうちは、咀嚼したり嚥下したりする機能の発達具合、消化機能の発達具合、栄養状態や出生時の状況など、それぞれのお子さんによって『食べて大丈夫なもの』『そうじゃないもの』が大きく異なるためです。」
一人一人体の状態が大きく違う子どもたちの食事は、年齢の数字を目安にひとくくりで考えるのはナンセンス。「いま、我が子がどういう状態なのか」を見極めながら判断することが大切だといいます。
では、乳幼児に「その食材を食べさせるか、食べさせないか」を迷ったとき時、ママは何をもとに判断すればいいんでしょう? 「生もの(サラダ、お刺身、魚卵)」「香辛料」「アレルギーリスクの高い食べ物」の3ジャンルを中心に聞いてみました。まずは生ものから!
生野菜の解禁は「奥歯の状態」をチェックしながら少しずつ!

「一般的には7、8カ月頃になると、トマトは皮と種を除いて粗くつぶせば、キュウリはすりおろすといった一手間を加えれば、生のままで食べられるとされています。ただ、この時期は生野菜にこだわらず茹でたり、煮たりして繊維をやわらかくしながら、食べられる野菜の種類を増やしていくのがオススメです。」
乳歯の奥歯は、目安として、だいたい1歳から生えはじめ、3歳頃までに生えそろいます。奥歯の状態や口の動きを見ながら、加熱時間を少しずつ短くしていくとよいのだそう。
「野菜の加熱時間を短くしていくと、だんだん生野菜に近くなり、歯ごたえが出てきます。お子さんが野菜を噛んでいるときのシャリシャリ、ポリポリといった音にも耳を傾けてみてください。しっかり噛めるようになっているかどうかの判断材料にもなりますよ。」
お刺身は鮮度と衛生管理が重要! 食中毒には注意して

「お刺身は時間の経過とともに鮮度が落ち、細菌数も増えます。体の機能が未発達な乳幼児は、細菌に対する抵抗力が弱く、食中毒を発症しやすい状態です。そういう意味で、腸炎ビブリオやノロウィルスなどのリスクがあるお刺身を食べさせるのはちょっと心配ですね。」
基本的には、しっかりと中心まで加熱して殺菌するのが安心だそう。では、お刺身解禁のタイミングは?
「明確な根拠はありませんが、離乳食が完了し、ほとんどの食品を食べられるようになった1歳半から2歳以降がよいと思われます。鮮度のよいお刺身が手に入り、お子さんが喜んで食べるようなら、初めは2〜3切れから、ぜひそのおいしさを経験させてあげてださい。お刺身は、種類よりも鮮度と温度管理、衛生的な取り扱いがされたものかどうかが重要です。」
しょうゆや塩で漬けてある魚卵は「塩分」にご注意を!

「いくらなどの魚卵も、お刺身同様、細菌などへの注意が必要です。さらに、食塩が多く含まれていることも見過ごせません。市販のいくらは、しょうゆや塩で漬けているものがほとんどで、いくら100gに含まれる食塩の量は2.3gに相当します。」
乳児用のベビーフードの塩分濃度は0.5%以下に、幼児用でも0.76%以下に調整されていることに比べると、いくらの塩分濃度2.3%は「かなり濃い」と梅原先生。
「つまり、大さじ1杯のいくら(約16g)に含まれる食塩の量は約0.4g。子どもたちの1日の食塩の目標量は、1〜2歳男児は3.0g未満、女児は3.5g未満、3〜5歳男児は4.0g未満、女児は4.5g未満(※)なので、大さじ1杯のいくらはその1割前後を占めるのです。」
「日常的に与えるものとしては好ましくありませんが、お祝いの席などで食べる機会があったときは、量や頻度に注意して楽しみましょう。」
(※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」2015年版より)
唐辛子やコショウなどの香辛料の解禁は急がずに

「お料理のアクセントとして食事を豊かにしてくれる唐辛子、コショウ、カラシやワサビといった香辛料。鼻や口唇、のどといった粘膜への刺激は強烈ですが、小さい子が食べたからといって毒になることはありません。」
「ただ、初めて食べるお子さんにとって未知の世界の味。香辛料の使い方によっては、その時食べた料理や食材に嫌な印象や記憶を持ってしまうこともありますね。」
そこで、使う場合には工夫を。たとえば、ハンバーグの肉の臭みを消すためにコショウを練り込むのと、最後に振りかけるのとでは、刺激の感じ方は変わります。
「この場合、練りこんだほうがまろやかに感じられるはずです。ご家庭の考え方にもよりますが、刺激の強い香辛料の使用はあえて急がず、なるべく控えるか、上記のように使い方を工夫してみましょう。」
タンパク質が含まれた食物は何でもアレルギーの原因になりうる
アレルギーが出やすい食べ物というと、つい、卵、乳、小麦、エビ、カニ、落花生、そばといった「特定原材料7品目」を思い浮かべがちですが、これらだけを警戒するのはまちがいだと梅原先生。
「タンパク質が含まれている食物はどんなものでもアレルギーの原因になりえるのです。しかも、症状が出るかどうかは、実際に食べてみるまでわかりません。」
「よく、離乳食で新しい食品を与える時は、『体調のよい平日の午前中に、新鮮な食材を、十分に加熱して、少量から与えること』が大切だといわれますよね。これらは、アレルギーの有無を確認しつつ、もし症状が出た場合はすみやかに医師の診察を受けられる条件なのです。」
乳幼児期にアレルギーが出やすい食物は…

「発症の原因となる食物や量は個人差がありますが、乳児期から幼児期早期に多く発症するのは、『鶏卵』『牛乳』『小麦』『大豆』など。ただ、その多くは年齢が上がると食べられるようになる傾向があり、3歳までに50%、6歳までに約80〜90%が食べられるようになります。」
一方、学童から成人になって新しく発症したという原因物質で多いのが、「甲殻類」「ピーナッツ」「そば」「魚類」「果物類」などの食物。これらの場合は、年齢が上がっても耐性を獲得しにくく、除去が長期間にわたることもあるのだそう。
「食物アレルギーは、実際に出た症状と食物経口負荷試験などの専門的な検査結果を組み合わせた、総合的な診断と治療が必要とされています。今は『食物経口負荷試験』を実施している医療機関も全国に増えていますから、もし何らかの症状が出たときは思い込みで除去食を行わず、専門医のもとで正しい診断と治療を受けることをオススメします。」
(食物経口負荷試験を実施している施設一覧:
食物アレルギー研究会ほかにもさまざまな食材がありますが、覚えておきたいのは「一般的にいわれている話と我が子の状態が一致するとは限らない」ということ。迷ったり、困ったりしたときは、我が子オリジナルの食育をするつもりで、栄養士さんに相談してみるのも手です。