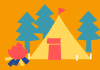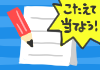子ども同士で遊んでいると、おもちゃの取り合いになってしまうことがありますよね。「取ったらダメ!」などと言っても、小さい子だと、まだわかってくれなくて困るもの。そんなとき、親はどんなふうにサポートすれば良いのでしょう。専門家に聞きました。
おもちゃの取り合いは、心の成長の証

「おもちゃを取り合うのは、物を『これは自分のもの』と認識できるようになった証。また、子どもに執着心が生まれたという心の成長の表れです。」
こう話すのは、ベビーシッターでイヤイヤ期専門家の西村史子さん。
生後半年くらいまでの赤ちゃんは、持っているおもちゃを取られても、「なくなった」という感覚なのに対し、8カ月〜10カ月児では、「自分のもの」という認識が生まれてくるのだとか。同時に執着心も育ってくるので、「自分のものを取られたくない!」と、取り合いになるそうです。
「さらに、2歳〜3歳くらいまでは、『自分のもの』と『他人のもの』の区別がまだきちんとつきません。気になったものは、すべて『自分のもの』だと思っているんです。」
「これは自分のもの」とお互いに思っていれば、取り合いになるのは仕方のないこと。とはいえ、力まかせで取り合いをすれば、ケガをする危険も…。親はどう介入すればよいのでしょうか。具体的な年齢別の対処法について、西村さんに伺いました。
0歳〜1歳半:叱らず見守って。ほかのおもちゃを提案も

まず0歳〜1歳半の場合、取り合いをする相手の年齢次第では、ケガへの注意が必要です。
「例えば、1歳と2歳では力の差が大きいので、押されたりしたときにうしろに倒れてしまわないよう、取り合いが始まりそうだなと思ったら、ママが小さい子のうしろにいてあげてほしいですね。」
この年代同士での取り合いなら、お互いさほど力が強くないので、大きなケガにつながる危険は少ないのだそう。取り合いになっても、近くでそっと見守ってあげていれば良いようです。
ここで注意したいのが、押した子を叱らないこと。
「押した子が、年上とはいえ2歳〜3歳の場合は、自分のしたことで相手がどうなるのか、ということがまだわかりかねる年齢。それにその子も『自分のもの』を守ろうとしているだけで、攻撃したいわけではないですから。」
では、おもちゃを取られて、泣いてしまった場合は?
「『このおもちゃはどうかな?』など、別のもので遊ぶことを提案してあげれば良いと思います。1歳半くらいまでは、まだ執着がそれほど強くないので、意識が他に逸れやすいのです。」
1歳半〜3歳:「約束」をつくる
1歳半から3歳になると、「自分のものと他人のもの」の区別がつくようになってくるのだとか。
「『取られたおもちゃは相手のものになる』という意識が生まれてくるのがこの頃です。また、『貸して』などの言葉も理解できるようになってきます。しかし、物への執着は増していますから、言っていることはわかるけど、相手のものになるのはイヤという時期ですね。」
つまり、この年齢同士の取り合いは、それまでのように、ほかのおもちゃで気を紛らわせるのは難しいということ。では、ママはどうすれば?
「取り合うという行為そのものは、成長の一つの証なので無理に止めなくていいと思います。でも、ケガをしないために、『物で叩いてはいけない』など、本当に危険な行為だけはしないよう、子どもと約束してください。」
さらに、「気持ちを受け止める」「できたことを褒める」「何をすればいいのか教える」の順番を守って、子どもに接することが大切だとか。
「おもちゃを取ってしまった場合も、『これを使いたかったんだね』と一旦子どもの気持ちを受け止めてあげてほしいんです。その上で、危ないことをしないという約束を守ったことを、『偉かったね』と褒めてほしい。そして『遊んで満足したら返そうね』など、次の行動を伝えます。気持ちを受け止め、できたことを褒めてあげてこそ、どうすればいいかという言葉も素直に受け入れられるのです。」
3歳〜4歳:事実を伝えて自分で考えさせる

3歳〜4歳は、だんだんと自分のやっていることがわかってくる年齢。この年代は、「事実を伝える」ことが大切だといいます。
「おもちゃを取って相手の子が泣いていたら『泣いてるね』と、今、見えている事実のみを伝えます。泣いた原因は理解している年齢なので、『あなたも○○ちゃんにおもちゃを取られて泣いたことがあるね』と、自分の経験を思い起こさせるのです。そこで『そのときはどんな気持ちだった?』『どうしてほしかった?』と、自分で考えさせます。」
「悲しかった」「返してほしかった」などと答えたら、「○○ちゃんも、同じ気持ちかもね」と言ってあげると良いそう。そうすることで、「相手にも気持ちがある」ことが理解できるようになっていきます。
では、取られて泣いているときは?
「まず『今、どんな気持ちなの?』と聞いて気持ちを受け止めてから、『どうしたかったの?』と問いかけてください。そこで『あのおもちゃで遊びたかった』など答えが出たら、『じゃあ、そのためにあなたは何ができるかな?』と、ここでも自分で考えさせます。」
「わからない」と言う場合は、「○○ちゃんが使ったら、次は僕に貸して、って言ってみる?」など、具体的な提案をしてあげると良いのだそう。ただし、「貸して」と言う場合は、「これで遊びたい!」という相手の気持ちもあるので、貸してくれることをゴールにはしないようにしましょう。
ママとの愛着関係がトラブル防止につながる
では、取り合いでのケガなどのトラブルを防ぐため、日常的にできることはあるのでしょうか?
「日頃から、ママとたくさん遊んでおくことです。ママとの信頼関係がしっかりと結ばれて、子どもの情緒が安定していれば、取り合いになってもそんなにひどいことはしないものです。」
少しやりすぎかな、と感じるような行為を子どもがするときは、遊んだり抱きしめたりといったコミュニケーションを意識的に増やすのも一つの方法だとか。
ママとしてはハラハラするおもちゃの取り合いですが、ケガをしないようにだけ気をつけたら、あとは「これも成長」と見守ってあげれば良いのですね。