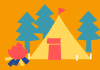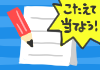子どもにとって好ましくないとは思いながら、つい、テレビをつけっぱなしにしてしまうママ、パパも多いと思います。しかし、そもそもテレビの視聴は子どもに悪影響はあるのでしょうか? また、良い影響を与える見せ方があるのなら、どんなものなのでしょうか?
実際のところ、テレビは子どもにどんな影響を与えるのか、子どもとメディアの関わりについて詳しいお茶の水女子大学の菅原ますみ教授に聞いてみました。
テレビは子どもに悪影響をもたらすのか?

テレビが子どもに悪影響をもたらす、というのは事実なのでしょうか?
「アメリカの小児科学会では、注意欠陥などとの関連性が疑われるとして、『0〜2歳といった乳児期の子どもにはテレビは見せないほうがいい』という勧告を出しています。」
「一方で、未就学児がテレビから受ける影響についての科学的な研究は2000年くらいから始まり、15年分の研究データが蓄積されつつあります。そこには、長時間視聴と注意力減退についてのみ弱い関連が見られる、という報告も一部ありますが、因果関係が見られなかったという報告もあり、結果が一致していません。」
「またADHDや自閉症などがテレビを原因に新たに発症するという報告は出ていませんし、テレビを多く見ていてもなんら問題が見られない子どもが多くいる事実も見逃せません。つまるところ、その勧告には
強い科学的な根拠が存在する、という状況ではないのです」
立場の違いもあり、検証もこれからという面がある模様。どちらが正しいということではありませんが、発達心理学はこうした実証的・科学的な調査研究に重きを置いており
今のところ「テレビの悪影響はほとんど無い」というのが見解です。
テレビ番組の内容については親がしっかり管理を
ただし、テレビ番組の内容については親がしっかりと管理する必要がある模様。
「暴力的、セクシャルな内容のテレビ番組からは直接の影響を受けてしまいます。子どもは大人が考える以上に物事を理解していますので、小さな子どもだからとあなどらず、注意が必要です。子どもにふさわしい教育的な内容の番組を選んで視聴するのが望ましいですね。」
「ただ戦争や犯罪なども現実社会の一部ですから、なんでもかんでも遮断するというのも考え物でしょう。ニュース番組などからそういった情報に触れるときには、年齢に応じて親がコメントを添えて一緒に視聴すれば、社会を知るよい機会となります。」
テレビの視聴時間は、どれぐらいが理想?
意外にも、子どもはテレビをそんなに見ていない
では、実際のところ、子どもは毎日どれくらいテレビを見ているのでしょうか? 調査によると、大人が考えているほど長い時間見ているわけではないようです。
「私が共同研究者として加わっている『“子どもに良い放送”プロジェクト』では0歳から11歳までのお子さんのいる家庭を調査しました。平均でみると子どもがいる部屋でテレビがついている時間は0歳で3時間13分、1歳で3時間24分と乳児期は確かに長いのですが、2歳では2時間44分と大幅に減り、その後5歳の2時間9分と徐々に下降します。」
「しかも、画面を見ていない『ついているだけ』の時間も多く、実際に見ている時間は『ながら見』を含めても一番多い1歳児で1時間44分程度で、あとは90分程度となっています。」
理想的な子どものテレビの視聴時間
専門家から見て理想的な視聴時間はどれぐらいになるのでしょうか?
「具体的に何時間であれば理想的ということはありません。気にすべきは子どもの『可処分時間』です。これはお風呂、ご飯、寝ている時間などを除いた、子どもの自由時間のことで、計測してみると、小さい子も意外と忙しく、だいたい5〜6時間といったところ。そのなかで、テレビ視聴がどれくらい時間を占めているかが重要です。」
「そこで実践していただきたいのが『視聴日誌』をつけること。一週間、どんな番組をどれぐらい時間観たのか、その他にも外で友達と遊んだ時間、室内でひとり遊びした時間、親と遊んだ時間、絵本を読んだ時間など、主要な活動について記録をつけておく。これで、全体の活動の中でどれぐらいテレビを見ているのか具体的に把握してください。」
テレビの視聴時間は、実際の視聴時間を把握して検討するべきだそうです。外でからだを動かして遊ぶ時間、絵本を読む時間、室内でおもちゃ遊びを楽しむ時間、テレビを見る時間、どれも子どもの成長にとって必要なもの。食品の栄養素と同じように考えてバランスよく配分するのが重要なようです。
「理想的な時間は特にないとはいえ、子どもの自由時間が一日5時間しかないと思えば、おのずとテレビを観てよい時間は多くても2時間以内に収束してくるのではないでしょうか。多過ぎるな、と感じたら一度テレビを消してみて下さい。ほかにも楽しい活動があることに気付けると思います。」
テレビはどのように見せるのがいいのか
テレビを絵本のように使う

子どもがテレビを見ているときの親の関わり方に、何かアドバイスはありますか?
「テレビを学習のために使うのであれば、子どもへの声がけ、問いかけがポイントになります。海外の研究で、3歳児を対象に番組内容の理解度、登場する単語の習得度について4つのグループを作り、サンプル番組を使って調査したところ、最も子どもの理解度や単語の習得に効果があったのが『親が子どもに問いかけをするグループ』でした。そして、番組出演者が(画面を通して)問いかけをするグループ、親が一方的にコメントをするグループ、親が一緒に見ていただけのグループ、の順に効果が下がっていくという結果だったのです。」
問いかけとコメントの違いですが「ウサちゃん可愛かったね」と感想を言うだけなのがコメント、「ウサちゃんはどう思っていたかな?」と考えて答える質問を投げかけるのが問いかけです。後者は『会話的な問いかけ法』というもので、考えて発言させることによって子どもの記憶に定着する度合いが高まるそうです。教育番組はお姉さんが画面を通して問いかけてくる構成にはなっていますが、それは一方通行にすぎず、親が子どもの反応をみながら問いかけることに勝るものはないのだとか。
「おそらく、絵本を読んであげるときには自然にこの会話的な問いかけをやっていることと思います。テレビも絵本のように使うことで、ただ観せるだけよりも学びの効果をあげることができるのです。」
子どもをだまらせるためにテレビを見せるってアリ?
子どもを構ってあげられない時、子守り代わりにテレビを流しっぱなしにしまうことがあります。これはよくないことなのでしょうか?
「忙しく手が離せないときにはテレビに助けてもらってもいいと思います。私自身、在宅で仕事をしているとき、子どもの好きな番組を集めた『鉄板ビデオ』を作っておとなしくしていて欲しいときに見せていました。このビデオは普段は見せず、ここぞという時に使っていたので効果は絶大でしたね(笑)。子育ては大変ですが心の余裕を持つべきです。楽ができる時には楽にして、笑顔を絶やさないのがなにより子どものためになりますから。」
平日は忙しくて子どもに構ってあげられない時間帯があるなら、そこはテレビに頼ってしまってもいい。代わりに寝る前に絵本を読んであげたり週末はいっぱい遊んであげればOK。それぐらいゆとりをもって考えればよいというアドバイスもいただき、ずいぶんと気が楽になりました。
結局のところ、テレビが子どもにどんな影響を与えるかは親次第。子どもにとっても、親にとってもためになるテレビの使い方を、各家庭で考えてみたいですね。